パルコ劇場で三谷幸喜の新作『なにわバタフライ』。
関西女性喜劇人の雄、ミヤコ蝶々の半生をモチーフに、芸と恋に生きた女性の姿を、戸田恵子の一人芝居で見せる。
なにしろ戸田恵子の演技が素晴らしい。肩に力を入れず、生き生きとした関西弁で、「人の笑う顔が見たい」がために喜劇に身を捧げた女性芸人を軽やかに演じてみせる。立居振舞いから風貌まで、ミヤコ蝶々とは似ても似つかないのだが、ふとした時(サングラスをかけた後、発する声!)に、ミヤコ蝶々その人としか思えなくなるから不思議だ。
一人芝居で笑いを生むのはとても難しい。いや、正確に言えば「笑い声」を生むのは難しい。
喜劇人の役割を、ごくごく単純にボケとツッコミに分けるとすれば、「笑い声」のうち、「笑い」を生むのはボケである。
しかし、「声」を生むのは、実はツッコミの方なのだ。
ボケの突飛な言動に対して、観客は心のうちで「それはこういうこと?」とほんの一瞬考える。その観客の心を代弁するかのように、ツッコミが入る。このツッコミが絶妙なタイミングであればあるほど、観客は思わず声を上げてしまう。「笑い」に「声」が加わる瞬間である。
そしてここに、一人芝居のコメディが難しい原因がある。
なにしろ舞台の上には一人きり、ボケたところでツッコんでくれる相手はいない。こうなると、観客の方も「笑い」をもてあましてしまう。「面白いんだけど、笑えなかった」という感想が生まれる所以だ。
これを解決し「笑い声」を生むために手っ取り早いのは、一人でボケとツッコミを演じることだ。
(例えば、一人芸人ヒロシの自虐的な台詞には、ボケとツッコミ(客観的な見方)が同居している)
ただしそれだけのパターンでは、2時間の舞台を持たせることは難しい。
そこは三谷幸喜のこと、何か策を練っているに違いないと思っていたが、今回、一番の武器として用意したのは「誇張」だったのだと思う。しかもこれが「一人芝居でしか成立しない誇張」になっているところが憎いほど上手い。シチュエーション・コメディという得意技が災いして、これまでは思うように使えなかったパターンの「誇張」を、ここでは存分に生かしている。
そして、波乱の恋を生きた女性芸人の人情劇という、通俗的になりがちな題材に、この「誇張」が加わると、”人生劇場”的な現実世界を突き抜け、一種ファンタジックな香りが漂い始める。まるで落語の登場人物たちが生きる世界のように、バカバカしい突飛な空気が舞台に生まれるのだ。
その突飛な空気は、ミヤコ蝶々の半生に「嘘」という新しい光を当て、逆に何倍にも輝かせてみせる。
これが思わぬ効果だったのか、それとも計算づくなのか・・・
そんなことを尋ねても、三谷さんはポーカーフェイスではぐらかすに違いない、のだろうなあ。
鑑賞メモ


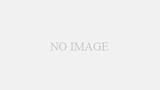
コメント
はじめまして。
ボケとツッコミという笑いの原点を視点に、この芝居について語っていらしたので、面白いなーと読ませていただきました。
「誇張」という表現での見方もなるほど、と思いました。
私は三谷さんが、私たち観客に挑戦状をたたきつけてるような気がしました。どこまで観客が自らの想像力でもって、この舞台を楽しめるか。それが「ファンタジックな香り」で「突飛な空気」なのかな?と管理人さんのレポを読んで思いました。
それと、私の観劇レポをTBさせていただきました。
るるりんさん、はじめまして。
コメントありがとうございました。
観客への挑戦という見方も興味深いです。
レビューも拝見させて頂きました。
初めての一人芝居で、ミヤコ蝶々という人を題材に選んだのは、自分自身への挑戦という意味もあったのかな?と思います。
偉大なコメディアンの人生を、ストレートにドラマティックな物語に仕立てるのはある意味定石かもしれないんですけど、喜劇人が喜劇人を描くと、どうしても仲間誉めと取られてしまいますし。
だから、直球勝負とは少し違った形で上手く描けないか、という試行錯誤があったんじゃないかな、と想像したりしました。
ところで堺雅人さんがお好きなんですね。
映画版『笑の大学』を観た帰り道、「座付作家役が堺雅人だったら、どうだったろう・・・」とふと考えました。