原作はクリス・ヴァン・オールズバーグの「急行『北極号』」(村上春樹 訳)。監督はロバート・ゼメキス。自分で言うのもなんだがこの『ポーラー・エクスプレス』、クリスマス・シーズンをとうに過ぎてから観る映画では断じてない・・・
この絵本の世界を映像化するにあたり、製作者が選択した表現方法は、実写やアニメーションではなかった。モーション・キャプチャーによって人間の動きを再現することで、デジタル技術を使いつつも血の通った温もりさえ感じられる、そんな写実的な世界を生み出そうと試みている。
しかし、現実の人間の動きを写し取られた登場人物達の姿が、妙にリアルでありながら細部の現実感に欠け、その「半端なリアル感」に居心地の悪さを感じてしまう。冒険と感動の旅へと向かう子供達も、とにかく表情が可愛くない。それどころか場面によっては薄気味悪ささえ覚え、とても愛らしいとは言えない。
この絵柄のせいで、すんなりと映画の世界に入って行けない人も多いのではないだろうか。
映画のテーマは非常に単純で、『クリスマス(という「夢」)は、信じる者に訪れる』というもの。その単純なテーマを軸として、ハラハラ、ドキドキのスペクタクル・シーンをこれでもかとばかりに盛り込み、1時間40分の作品に仕立てている。
ところが、テーマの部分と活劇部分とがお互いに独立していて、噛み合っていないところに弱さを感じる。なにしろ原作はわずか29ページの絵本。映画化にあたり、見ごたえのある迫力満点のシーンを新たに想像する必要があったのだろう。なおかつそれらのシーンを、テーマが生む感動への橋渡しとして生かすためには、原作を切り崩し、新しい挿話を入れながら、上手に再構成しなければならない。
努力の跡は見えるものの、繰り出される活劇の間を縫って、途切れ途切れに物語が進行してしまうように感じられる点を払拭するには至らなかったように思う。
と不平を述べてはいるが、ではこれが退屈で仕方がないかというと、それなりに飽きずに観られてしまうのが不思議だ。その原因を考えるに、この物語には冒頭に書いた「半端なリアル感」が不可欠だったのではないか、と思い至って、一人合点がいった。
本作に登場するミュージカル・シーンや、大勢のエルフが歓喜の声をあげるクライマックス・シーンは、もしディズニーであれば、得意の擬人化をタップリと使い、目まぐるしい場面転換をともなって表現するだろう。ところがこの映画では、こうした派手な見せ場でさえも、一定のリアリティを保ったままに演出されている。
もし、アニメーションによる飛躍した表現を使用したとすれば、夢や希望を礼賛するという甘いテーマが、更にファンタジックな甘い演出でコーティングされ、純粋な子供向けの作品になったに違いない。
そうではなくリアルな表現を選んだがゆえに、薄氷の上を進むがごとくではあるものの、何とか大人の視点でも100分を観続けることが出来るのではないだろうか。
全米では公開当初こそ興行収入が伸び悩んだものの、長い間一定の動員を保ち続け、ついにはトータルでそれなりの興収を得たとのこと。これは、大人が映画館に足を運び続けたという事実を物語るものかも知れない。
映画化にあたっての立て役者は、なんと言っても企画者でもあるトム・ハンクスということになるだろう。劇中五役を担当し、まさに独壇場の感がある。声色を変えて様々な役柄を演じ分けてみせる、極めて真っ当な声優ぶりだ。
『アラジン』で魔神を演じたロビン・ウイリアムスの、多芸を駆使したワンマン・ショー的な声優ぶりと比較してみるのも面白いかも知れない。
鑑賞メモ
錦糸町シネマ8楽天地8


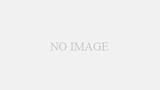
コメント