
今や宮崎駿作品と並んで、誰でも安心して観られるブランドにまで成長したピクサーの新作。
ピクサー作品が子供だけでなく、大人の心へも訴えかける力を持っているのは、いつでも「郷愁」を隠し味として用意しているからだ。
たとえば『トイ・ストーリー』では西部劇が娯楽として隆盛を誇った時代に、『モンスターズ・インク』では大人達がかつてクローゼットを恐れた子供だった頃に、それぞれ心がリンクするように、上手に創られていた。
そして今回はスパイ・アクションへのオマージュ。オープニングとエンディングでは、往年のスパイTVドラマのようなテイストで盛り上げている。
監督・脚本が『アイアン・ジャイアント』を手がけたブラッド・バードなので郷愁はお手のものだし、もっと甘甘な話になるのかと思ったら今回は抑えめで、誰でも楽しめるエンターテインメントに終始しているのは、やや意外だった。
かつて誰にも愛されたスーパーヒーローでありながら、ヒーローとしての活動を禁じられ、今や一般市民としての生活を余儀なくされているMr.インクレディブル。華やかな栄光の日々にすがりつき、ストレスに苛まれながらの生活を続ける中で、家族もそれぞれ悩みを抱え、家の中はどことなくガタピシと音を立て始めている。
この一家の様子に、一般市民の有り様を読みとるのは難しくない。つまりこれは、悩めるヒーロー一家の姿を借りてはいるものの、その実、アメリカが得意とするファミリー礼賛の物語なのだろう。スーパーヒーローでさえ、自分一人では生きていけない。家族が力を合わせて困難に立ち向かうことこそが大事だ、というわけ。
ちなみに原題は”The Incredibles”。つまり「インクレディブル一家」で、このタイトルだけを見ても、家族がテーマと分かるようになっている。これが邦題では『Mr.インクレディブル』となったわけで、原題の意味が上手く伝わっていないんだが、『インクレディブル達』としたところでちょっとサエナイし、まあ致し方ないところか。
日本語という言語は語彙が豊富な一方で、短い語数でビシッと決めるのが不得手だったりする。映画の題名はそれが顕著に表れる好例かも知れない。
いつものピクサーらしくスピード感溢れる活劇の連続で楽しく観られるのだが、ただし今作、ちょっと脚本の練り込みの足りなさを覚える部分も少々見受けられた。たとえば、悪役の描き方。後半で悪の真の目的が明らかになるが、それを知ってもなんとなく「別に良いんじゃないか?」という思いが残った。言ってみればバットマンだって実は、心の底でああいう感情を抱いているんじゃないかとも思うし。
確かに悪行といえば悪行には違いないんだけども、「倒されるべき絶対悪」めいた扱いにして良いものだろうか?万人受けするために勧善懲悪のストーリーにする必要があるとは言え、もうちょっと悪のムナシさというか、人間的な弱さみたいなものを描いても良かったのではないかなあ…。
それとこのプロット、どことなく『スパイキッズ』に近いような気もしたんだけれど、その辺はどうなんでしょうか。
鑑賞メモ
錦糸町シネマ8楽天地5


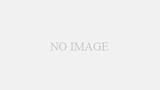
コメント