
筒井康隆作の小説『時をかける少女』と聞いてぼくと同年代の人達がまず思い出すのは、1983年に大林宣彦監督、原田知世主演によって映画化された作品だろう。更に一世代前の人達には、『タイムトラベラー』の題で放映されたTVシリーズが記憶に残っているかもしれない。この小説はこれ以外にも何度かTV化されているし、また角川春樹がメガホンを取った再映画化も記憶に新しい。
時代に応じて、アイドルの登竜門的な役割を果たしながら何度も映像化され続けている小説ではあるが、これまで映像化された作品群では、いくつかのバリエーションはあるものの、過ぎ去れば二度と帰っては来ない時間の流れが育むある種の「儚さ」を、作品の根底に置いているスタイルが共通していると思う。
しかし今回アニメーションとして再々映画化を果たした本作は、それまでの『時をかける少女』とは一線を画していると言って良いだろう。
時をかける能力を得ることになる女子高生、紺野真琴は、現代っ子そのものと言える活発なキャラクターとして登場する。能力を得てしまったが故の不幸さや、オリジナルにあった「繰り返されることの空しさ」など、彼女の立居振舞いからは微塵も感じられない。特殊能力にまつわるメランコリックな影の部分を思い切って切り捨て、問題解決へ向けて一直線に突き進む真琴の姿勢が醸し出す爽快感で置き換えたこそが、本作の生命線だと思う。
ただし一方では、過ぎてしまえば取り戻すことの出来ない、かけがえのない日常を描くことで、青春映画としての体裁もきちんと整えられている。真琴が友人とキャッチボールをしながら過ごす安寧な日々の穏やかさ。「繰り返される」似て非なる日常、その貴重な瞬間瞬間を掬い上げることも忘れてはいない。
それにしても、クライマックスシーンで真琴が、同級生の千昭に向けてつぶやく台詞の素晴らしさ!巻き戻しの効かない不可逆の時間に正面から対峙することこそが美しいのだと、その台詞は高らかに謳い上げる。
若さを体現する真琴にとって「時」は、振り返って懐かしむべき対象などではなく、現在進行形で明日へと「かける」ための広大な平原なのだ。
鑑賞メモ
銀座テアトルシネマ


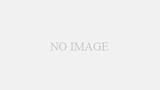
コメント