アルノー・デプレシャンといえば、映画ファンならその作品を見逃せない映画人の一人・・・と思いながらも我が身を振り返ると、恥ずかしながら、あまりに過去作を観ていないことに、改めて気が付かされる。
これで映画ファンを名乗るなんておこがましい限りで、恥ずかしくなることしきり。
フィルモグラフィの中でちゃんと観ていると思われる作品は「クリスマス・ストーリー」ぐらいで、これにしても物語のプロットすら記憶が曖昧なほど。ダメだなあ・・・思わず襟を正さずにはいられない。
『映画を愛する君へ』は、デプレシャンが映画と向き合ってきた、その半生を題材にした、シネコラージュのような作品。
そのコラージュは19世紀、映画誕生の歴史から始まり、続いて幼少〜青年時代に映画へのめり込んでいく様子が、時系列に描かれてはじまる。ただしそこに、純粋な技術発展の経緯や、数々の名作に対する系統立てた映画史整理といった意図は皆無で、極めて私的な映画タペストリーを編んでみた、といった様相だ。
アメリカで発明された、フィルムによる「映画」というメディア技法が、フランスのリュミエール兄弟とその後継者たちによって「シネマ」という芸術に結実した、という経緯が、この前半で語られていく。
このパートは、デプレシャンが幼少期に見た活劇に代表される、まさに蜜月時代たる映画全盛期を舞台にしているが、単に好きな映画の思いを集めて嬉々とするような能天気さに身を浸したまま、映画が幕を閉じるようなことはない。
後半になり、時代が第二次大戦前後から20世紀後半に至ると、絶え間なく繰り返される政治運動や抗争の中で、映画もまたそれら社会問題と無縁ではいられず、政治的な不穏さに縁取られ始める。「現実を映す」機能を持つ映画が、必然的に帯びざるを得ない、時代を映したやや暗めのトーンへとシフトしていく。
そして終盤は、ビデオとデジタル技術の勃興によって、フィルムが急速に脇へと追いやられていく時代。
「たとえフィルムというメディアによる映画技法が忘れられたとしても、”シネマ”そのものの技法は我々の血の中に脈々と息づき続ける」そのように語る、ニューヨーク在住の評論家、ケント・ジョーンズの言葉が、映画終盤のトーンを決定づけている。
うっかりするとこの言葉は、映画の歴史が永久不滅に、我々の中で欠くことなくいつまでも残る、というセンチメンタルな響きに聞こえてしまうだろう。
しかしながらこの言葉は、シネマの歴史のど真ん中に生き続けるデプレシャンにとって、「われわれはシネマの血脈から逃れられない、だから、私は映画を作り続けなければならないのだ」という決意の表れのこだまとして、援用されているように思う。映画とは、彼の中では自分の運命を決定づけている刻印である。それは、今後の映画制作の方法を見つめ直していると劇中で語っていたデプレシャンにとっての「覚悟」であり、所信表明であるように思えてならない。
「映画を愛する君へ」という、なんとなく映画ファンの感傷を呼ぶような邦題を、国内配給会社が、どれほどの思いを乗せて付けたのかはわからない。
原題は”Spectateurs!”、直訳すれば「観客たちよ!」だ。
監督であるデプレシャンもまた観客から出発している、だからそんなわたしも含めて、映画を成り立たせる要素としての観客もまた、その刻印から逃れ得ないのではないか?と、デプレシャンは語りかけているのではないだろうか。
観客無しくて成立しないシネマという芸術継続のためには、観客もまた共犯となり、同じ刻印のもとで、映画を観続けざるを得ないことになるのだから。
さあ、いま、この映画の観客であるあなたは、いったいどうするのか?
スクリーンの向こうから、デプレシャンという映画人が、いたずらっぽく目配せをしている気がするのだ。


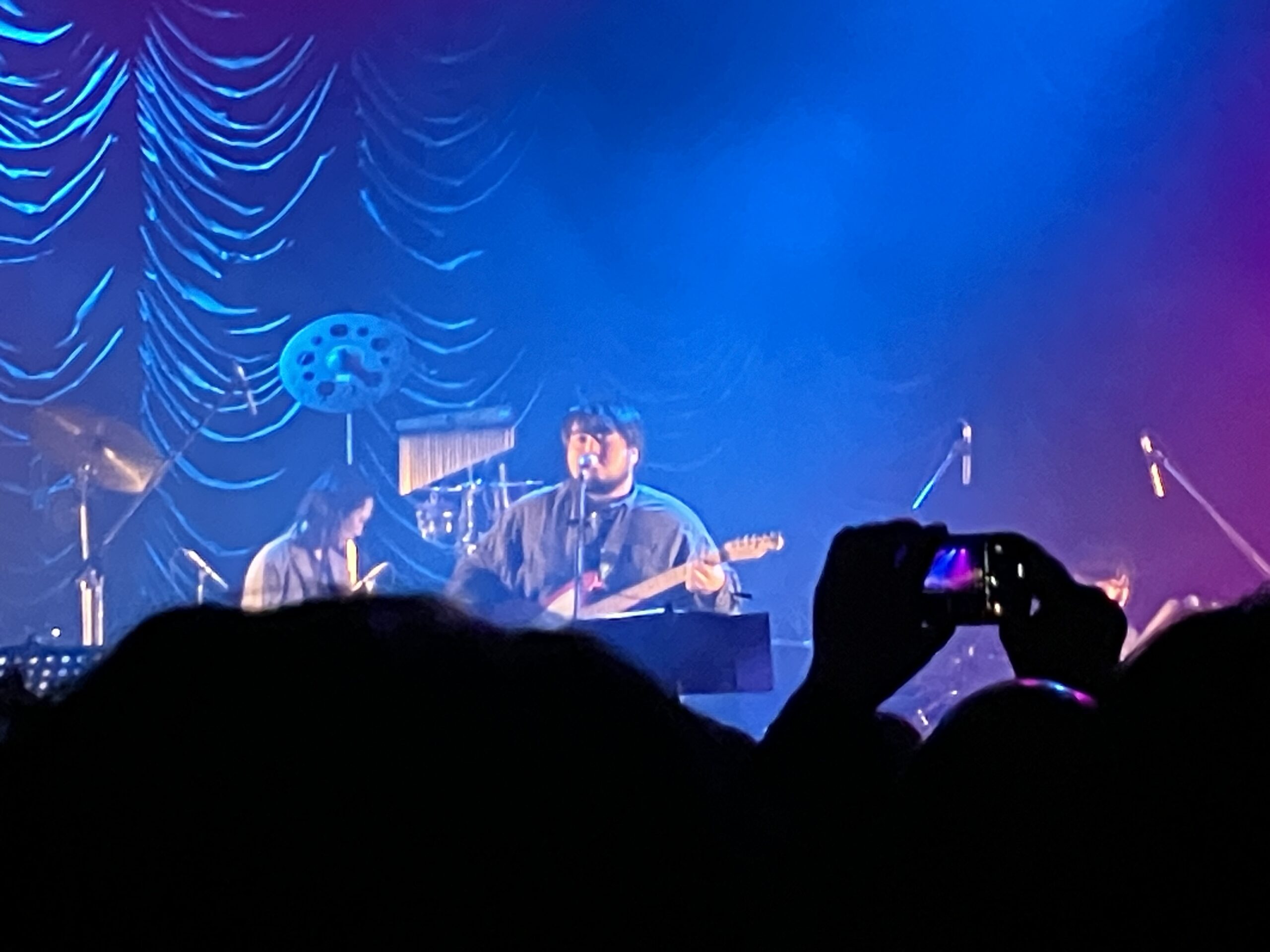
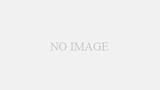
コメント