安藤奎の芝居は、恥ずかしながら、昨年開催された『寸劇の庭』での中編コントを見たのが初めてだった。勉強不足がたたり、新しい世代の芝居が追いかけられていないので、ちょっと何とかしないと・・・という気持で、観劇に至った次第。
しかし、チケットを買ったちょうどその日に、前作『歩かなくても棒に当たる』の岸田國士戯曲賞受賞が決まったことで、もともとすでに人気劇作家だった彼女への注目度が、さらに上がった気がする。そうしてみると、今回のチケット購入のタイミングは、結構ラッキーだったのかもしれない。
会場の三鷹市芸術文化センターも、かなり久しぶり。前回来たのがいつだったのか、まるで思い出せない。『ヤング・マーブル・ジャイアンツ』以来かも、と思って調べてみたら、あれは吉祥寺シアターだった。
(まるで関係ないが、『ヤング〜』もう一度観たいなあ。映像化されてほしい一作なのだが、内容が内容だけに、まあ無理なのだろうかなあ・・・)
上演中や、上演追加の可能性があるなど、まだ人の目に触れる可能性のある芝居について、あまり細かい設定や物語に触れたくはないし、また今作のように物語中心というよりは、場面場面をカットの連続のように積み重ねていくような構成の芝居について書くことは、そもそもなかなか難しい。
自分が今回、最も気にしていた笑いの要素について言えば、鑑賞前にはもうちょっとコントらしさと言うか、笑いをそこここに厚く織り交ぜた作品を想像していた。
実際、観ての結果は、もちろんそうした要素は含まれてはいるものの、無理に笑いを作ろうとしておらず、シチュエーションとセリフ回しで笑いを滲み出させるような手法に軸足を置いているのだな、と受け止めた。
中編のコントと、中編(70分)の芝居、2本しか観ていない状態で、断じるような書き方も我ながらどうかと思うけれど、これらの2篇に共通する視点のようなものを何とか抽出してみると、こんな感じになるのかなと思う。
- 世界は、個人個人の考えや見方に基づいて自営/自衛されている小さな世界の集合体である
- 個人世界は、意図しようとしまいと、他人を自分の世界に取り込もうと(引き寄せようと)し続ける
- ときに、ごく些細なことがきっかけで、取り込み/取り込まれる関係は、容易に変化する
これらの根底にある考え方をごくごくストレートに書くなら、「人間は分かり合えない」ということになるのかもしれない。こんな言葉、もはや風化寸前の陳腐な表現だけれど、逆に言えば、一般通念として充分な市民権を得た考え方だということになるのだろう。
その「分かり合えない」という共通の前提事項を出発点にして、「分かり合えなさの質量」や、「どんなふうに分かり合えないのか」「果たして分かり合えることはあるのか」を、いかに描くのかが、すなわち現代の作家にとっての独自性であるということになっている、気がする。
自分と他者との思いの違い、それぞれが持つ世界観の乖離、そうした、2025年版の個人主義とでもいうべき社会の成り立ち。それに加えて、個人と集団の意識が複雑に混ざり合う特異な場としてのインターネットについても、わずかながら言及されているのは興味深い。
ネットで拡散された言葉は、発した本人による意味合いをどんどんと離れ、それを受け止めた読み手の個人世界に容赦無く取り込まれていく。しかしそれは、個人の中にだけ沈殿するのではなく、ネット上に生きる、ある種の集団自我のような形に徐々に収斂されていき、不可思議な同調圧力のようなものへと姿を変えていく。
作中の登場人物たちも、それぞれが心の中に持っている世界が、互いに付かず離れずを繰り返しながら、互いが発する意見や言葉に、時に影響され、時に影響を与えられ続けている。そうした関係の結果、何名かの意見がふと同じベクトルを向くことで、集団の中の「大勢」を形作りはじめ、「少数」側と対峙する、そんな時期がやってくる。そして「大勢」の側が出来上がったとたん、「大勢」側の世界観が、集団の中で幅を利かせ始めるのだ。
ただし、そうして幅を利かせた「大勢」の趨勢は、ふとしたきっかけでほぐれ、今度はまた別の「大勢」が現れる。この時、自分が今度は「大勢」の中にいるのか、「少数」の中にいるのか、それはその都度変わっていく。現代人は、この恣意的に関係性が再構成される繰り返しの中に、身を潜めて生きている。
こうして、登場人物たちそれぞれがみな、自分の確固たる世界を持っていそうな、持っていないような、不安定な関係を保っている中で、お互いの世界は、少しずつ影響の授受を余儀なくされていく。
しかしこの作品がユニークなのは、だからと言って、同調圧力は巨悪、「大勢」の力は害悪、そう断罪して話を終えるような、そうそう単純な話にはなっていない点だ。
話が終盤にいたると、こんな考え方へと辿り着くような世界観も見え始めてくる。
- 人間は、圧の強い他人の世界へと容易に取り込まれてしまうように見えるが、実はそうでもなく、自らの世界を維持し続けようとする力は、思いのほか強い
- こんな個人主義的な世界でも、個と個の世界同士が、重なり合い、共鳴し合う部分は、確かに存在する。それがどんなに狭い領域であっても
誰も彼もが自分の世界をいっぱいに膨らませて生きている中で、”遠巻き”に見ることは、逆に難しくもある。日本人の脊髄に刷り込まれている感のある「触らぬ神に祟りなし」「見てみぬふり」が有効に働くこともあるはずだけれど、現代人にとって、「神に触らない」ことそのものが、難しくなってきているのかもしれない。
「見てみぬふり」をしようとしても、周囲は、自分の世界に取り込もうとする他者で満ち溢れているし、そうなると「見てみぬふり」をするには、他者の世界に容易に取り込まれてなるものか、と、自ら依って立つ自分の世界を踏み締めて、足を踏ん張っていなければならない。
でも、そう思うそばから、ふとしたきっかけで、今まで自分が足を付けていた地面だとばかり思い込んでいたものが、実は泥の塊のように感じられはじめ、それに気づいた瞬間から踏ん張りが効かなくなったりもする。それでもまだ、自分の足元が固い地面であると信じ、立ち続けることが、果たしてできるのか?
そんなふうに思うと、他人同士の世界が交わり、共感が育まれることなど、奇跡のように思え始めてくるのだが、それでも本作では、世界同士の論理積のように重なり合う色濃い領域が「確かに存在する」のだと、決して声高にではなく、ひそひそ声で語られる。
この、人と人との思いが重なる領域の存在の発見を、いわゆる「前向きな」「ええ話」に仕立てあげることも可能だが、本作は決してそうはしない。そんな予定調和な盛り上がりなど許されないと言わんばかりに、「ひそひそ声」、とても小さな声で語られるのだ。そんな小さな声でも、その声は、観るものの耳に確実に届くよう、演出されている。
「心の底から分かり合える」ことなど、もはや夢また夢の社会の中で、ほんの一瞬、ほんのわずかなふとした瞬間に、とても他愛もないことがきっかけとなって、お互いが「同じ穴に住んでいる」ことを、仄かに共感するときが訪れる。
その共感こそは、複雑な現代に生きている人間という動物にとって、オアシスに溜まったひと掬いの水のような、貴重な感情のゆらめきなのかもしれない。
鑑賞メモ


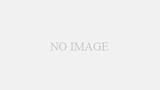
コメント