子供用TVアニメの映画版、というと、いわゆる「キャラ変」がどの程度許されるか?という問題がかならずついて回ることになる。
たとえば「ドラえもん」の場合、TVでは安定の?いじめっ子であるジャイアンとスネ夫が、映画版になったとたん、非常に協力的な「良き相棒」に変化する、というあれだ。
子供たちの集中力を切らさない短編(10分程度)の多い子供用TVアニメと違って映画は、2時間近くの長尺の中で観客を惹きつけ続けるための設定やプロットが必要になる。
その王道といえば、「ふだんはそれぞれ欠点を持つキャラクターたちが、共通の敵に対峙して、共に力を合わせて立ち向かう」というもので、どんな作品でも、映画版は自然とこの構図に沿った展開になるのは避けられないところだ。
この流れの中では、ジャイアンやスネ夫も力を合わせて戦うべき仲間の一員に組み入れるのが自然だし、またそうしなければプロットが崩壊してしまう。それどころかむしろ「いじめっ子に見えたけど、本当は仲間思いの良いやつ」として描かれる彼らの姿が感動を呼んだりもするわけで・・・必然的に、このキャラ変は不可欠なものになっていったのだろう。
(だから、最初から優等生で、文武両道合わせ持つ出来杉くんは、「力を合わせて戦う」キャラとしての位置付けが難しく、必然的に映画版では影が薄くならざるを得ない)。
この「クレヨンしんちゃん」も、映画版では同じことが起きるのだが、一番はじめに「キャラ変」がクローズアップされるのは、やはりしんちゃん自身だ。
おふざけキャラのしんちゃんが映画で見せる真剣な表情や、家族への想い。それ無くしては映画版はもはや成立しないのだと思うが、とはいえこのキャラ変を推し進めすぎてしまっては、なんだか感動を強要しようとするかのような、あざとさが目についてしまう。
その「キャラ変」された人物たちを、TVアニメにキャラへとどのように着地させるか、という点についていえば本作は、ほど良い感じにバランスが取れていると思う。
「人間は多面的な生き物だから、常に”他人から期待される自分”という一側面だけに囚われ続ける必要はない」
端的に言ってしまえばこれが、本作の主旨だ。そして、この主旨を体現する役割を任されたのが、主要キャラの一人である「ボーちゃん」。ふだんのボーちゃんは石を愛でる穏やかな性格だが、映画の中で、ふとしたきっかけで自分を解き放った結果、”ボー君”=”暴君”のごとき存在に変わり、”ボー若無人”な振る舞いを続けることになる。
そんなボーちゃんの変化を目の当たりにした幼稚園の仲間達は、ふだんのボーちゃんに戻ってくれることを願いつつも、「でも・・・今のボーちゃんが本当の姿で、そうあることをボーちゃんが望んでいたとしたら、ぼくたちはどうすべきなんだろう?」「ぼくたちは、本当のボーちゃんの、何を知ってるんだろう?」と思い悩むことになる。
そうした「自分らしさの肯定」のような「大人のテーマ」を、この映画は観客に対して、押し付けがましく強いたり、諭したりすることはない。
つまり、「暴君」化したボーちゃんのキャラが「本当の姿かもしれない」から、一方的な目線で他人を見ることを止めよう!などと、「大人の目線で」過剰に肯定したりすることはしていない。
最終的にはボーちゃんを含めた仲間達は、ごく自然に、いつもの仲良しグループに戻っていく。
一見すると、提示したテーマや課題を途中で放り投げてしまっているように見えなくも無いが、これが子供向けのアニメであることも考えれば、この辺の「適度に済ます」のも、有効な制作方法なのかなとも思う。
一方で残念なのは、この「自分は自分のままで良い」というテーマを支え、補完するはずの、映画独自のゲストとして登場するキャラクターたちが、ほとんどと言って良いほど機能していないことだ。
ゲストキャラの一人である女の子”アリアーナ”(声:瀬戸麻沙美)は、フェスを通じて国中に名の知れるところとなったという設定だが、周りから期待される自分像に囚われ続けていて、本当の自分を出すことに臆病になっている。彼女のキーワードは「希望=希ボー」といったところか。
(このキャラクターには、「ありのままの・・・」というあの映画が透けて見えるのだが、穿った見方だろうか)
彼女は、しんちゃんたちとボーちゃんとの接し方を通じて、自分が「ありたい自分」から離れてしまっていることへの反省へと辿り着く・・・のだが、この揺れ動く心の振り幅を実感できるほどに、彼女の心情を描くシーンが用意されているわけでもない。もう少し、彼女の気持ちが転換を起こす具体的な場面を準備する必要があったのではないだろうか。
せっかく大掛かりなフェスのシーンもあるわけなので、これをうまく使えば、大きなクライマックスに繋がる彼女の見せ場が準備できたはずなのに・・・。
また、もう一人登場するゲスト、”ウルフ”(声:賀来賢人)は、更によく分からないキャラだ。大富豪で、自分にふさわしい「相棒=相ボー」を求めている、ということなのだが、それが何のためなのやらまったく不明。
彼もまた、しんちゃんたちの姿を観て自分を奮い立たせる様子が描かれはするものの、どうしてそういうことになるのか、その心持ちが一つも理解できない。まるで「相ボー」という言葉遊びを実現するためだけに作られたキャラクターのようだ。
TV版とは違う様子で暴れまくるボーちゃんの姿は新鮮だし、敵対するしんちゃん達とボーちゃんに「共通の敵」が現れるその展開は、うまく作ったなあと感銘を受けたのだけど・・・
かえすがえすも、ゲストキャラの造形をもう少し掘り下げられていれば・・・と「惜しい」気持ちでいっぱいになる。
懐かしい主題歌の登場など、しんちゃんを長く見ている人たちを楽しませるための道具立てはそれなりに揃っていることを考えると、あと一息という印象だけが残る、そんな一作でした。
鑑賞メモ


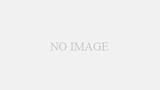
コメント