『パラサイト』で、ついにオスカー獲得までも果たした、ポン・ジュノ監督の最新作。
近未来の地球で、裏社会のマフィアに追われる身となったミッキーは、追っ手から逃れるため、他惑星開拓用のロケットで地球脱出を図る。
満員に近いロケットへ乗り込むために、”エクスペンダブルズ(EXPENDABLES)”=”消耗品”として乗船することを選択した彼は、以降、数々の危険な職務で命を落とすたびに身体を「再プリント」され、記憶を移植されながら生き続けていくが・・・
ポン・ジュノ監督の映画では、劇世界の背景として、ある種の権力構造が常に存在している。そして彼の映画は、その権力構造が覆され、破壊されていく(あるいは破壊が失敗に終わる)様子を、映画を先へと進めるためのモーターのような駆動力として利用し展開していくという特性を持っている。
そのため、彼の作品が、政治的な香りをふんだんに振り撒いたり、何らかの社会批判や主張を声高に叫ばんとする色を帯びたとしても、まったく不思議ではない。
しかし実際に出来上がった作品は、あくまでエンターテインメントの範疇に留まり、「観客を楽しませる」という目的を達成しながらも、観終えた観客の胸の内に微妙な掻き傷を残していく。そんな手際の良さこそが、彼の映画を特別な存在へと押し上げている所以なのだろう。
この権力構造は特に、監督が海外へ進出してからの、直近2作に顕著だ。
海外進出第一作となった『スノーピアサー』では、ある列車の中の前後車両の関係を社会階層に見立て、主人公が最下層である後方車両から、上層である先頭車両を目指して進みゆく、その「横移動」を、物語を先へと推進させるための機構として利用していた。
また前作『パラサイト』では、半地下の家屋に住む無職の一家が地上世界へと這い上る「縦移動」によって、上流階級者の家族に取って変わろうとする。一旦は階層の塗り替えに成功したかに見えた下層の住人たちが、かりそめの上層地位を維持し、守り抜くための労力や紛争が、サスペンスの根幹をなしていた。
また個人的に大好きな「グエムル」では、米国を頂点とする社会を暗渠で肥大した怪物の姿になぞらえ、これに対して市井の人々が、社会の最小単位である「家族」を武器として携えて対抗する、という構図に落とし込んでみせた。
(それにしても、米国批判を隠そうとしない監督に、映画制作の土壌を与えた”アメリカ”には、古き良き懐の深い米国らしさを感じて、ちょっと好もしく思う。
もちろんそれは、映画会社の経済的な企業戦略あってのことだとは思うけれど)
では、この『ミッキー17』はどうなのか?
一人では取るに足らない存在であるミッキーが「再プリント」され、何名も集まることで、階層構造と権力主義とに立ち向かう・・・
鑑賞前に、宣材ポスターなどを見て、そんな物語を想像したのだが、しかし実際の映画は少々異なる性質を持つものだった。
亡くなるたびに「再プリント」され、いくらでも代わりの効く存在であるミッキーは、使い捨ての労働力としてしか見なされない下層市民の象徴であって、船内で上流階級に位置する開拓リーダーのマーシャルとその一派との間には、揺るぎない階層が形成されている。
しかし、この物語の構造は、そうそう単純では無い。複製されたミッキーは、毎回全く同一の人物というわけではなく、性格が微妙に異なることもある。つまり、「その他大勢」であるはずのエクスペンダブルですら、実は多様性と個性とを持った、極めて人間らしい存在なのだとみなすことができるのだ。
「その他大勢」の中に存在する個性の尊さでもって上級階層に対峙する、そこに『ミッキー17』のユニークさがあると思う。
マーシャルをはじめとする集団が船内で謳い上げる”One and only”の言葉が、皮肉にも、使い捨ての多数であるはずだったミッキーの美しさを、称える言葉としても聞こえ始めてくるのだ。
しかしこのような構造に則って展開する物語は、中盤以降、迷走と停滞とに支配され始める。
数々の事態に見舞われて右往左往し続けるミッキーに比べて、彼と対峙するはずのマーシャルは、惑星に到着してから、何をするでもなく、相変わらず船内にとどまり続けるのみだ。
市長のセリフのそこかしこから、彼が「純粋で高級な人間社会」「自分を頂点とする絶対的な世界」の構築を目論んでいることが読み取れる。植民地移住を通じて、社会創生を成し遂げようとする野望に満ちていたように見えたはずの彼(そして彼ら)だったが、そのための具体的な行動を起こすようには見られず、船内でじっとしているだけ。
マーシャルの望みの中心は開拓になどあるのでは無論なく、自らの権力の座を維持することこそが大命題なのだから、惑星に着いてしまえばそれ以上の行動など不要なのだ、という解釈は、ある意味では成り立つようには思う。
しかしそれでは、映画そのものもそこで歩みを止めてしまうわけで、この中盤から、サスペンスを持続させるための根本の仕掛けが定まらなくなっていることが、この映画の決定的な停滞を生んでしまったのではないか?
ミッキーを食事の実験台として利用しようとするシーンも、いずれ惑星上で構築されるかもしれない立国のための準備と見えなくもないが、その場面が、マーシャルの野望実現のための行動を表していると見るには、あまりに道具立てが弱すぎると思う。
そうした停滞の中でも、そこはポン・ジュノのこと、短いサスペンスを生む設定とシーンとの積み重ねで持続させようとしてはいる。それらはある程度、功を奏しているようにも思えるが、停滞を無理に進めようと細かいギミックを積み重ねたために、全体のプロットが複雑になり、行き先がどこなのかが分からない不安感ばかりが膨らんでしまったように思えるのだ。
不自然に咳き込むマーシャル、ミッキーたちを追うマフィアの手先の暗躍、ナーシャはなぜミッキーを愛し、カイはなぜミッキーを誘惑しようとするのか。そしてラスト近くでミッキーが見た、幻影にも似た夢のような場面は?
これら非常に思わせぶりな描写の数々は、総体として、消化不良を起こしてしまっているように思える。各々の描写について、ひとつひとつ「こういうことか?」と解釈を施すことは可能だが、それはまるで、何組ものジグソーパズルから、それぞれのパズルの中では組み合わせることのできる何ピースかずつを持ち寄って、一つの絵を作ろうとしているかのような、そんな「木を見て森を見ない」感が生じている気がするのは残念だった。
最後は唐突に、あまり関係ない話になってしまうが・・・
映画の中で描かれる上流階級の食事シーンで、時に登場人物が、ほとんど生のような、赤々した肉を食べていることがあるけれど、なぜあんなにも赤い肉が出てくるんだろう?
見ていてちっとも食欲をそそられず、むしろ気分が悪くなりそうなのだが、それが演出上の狙いどおりなのか、あるいは、本当に旨そうな肉に見せようと思ってそうしているのだろうか?この映画では演出効果どおりなのかもしれないが、それにしても赤すぎる・・・
ちなみに自分の記憶の中で、グロテスクさの際たる例は、『寄生獣』で浅野忠信が少量の肉を、ナイフとフォークで品良く食べている場面。あの肉は、それほど赤くはなかったものの、ローストビーフが更に灰色がかったような色をしていて、不気味の極致。
もちろんこのシーンは、演出上、狙って不気味に見せているわけだが、その意図したであろう効果以上に不味そうに見えてしまい・・・ということで、妙な意味で印象に残る場面だった。
鑑賞メモ


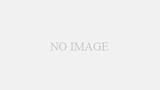
コメント