用事や仕事の合間に2,3時間の隙間がポッカリと空いて、何かしらで時間を有効に使おうと思う。
そんな時に使う「寸暇」という言葉を、ついぞ目にする機会が本当に少なくなった。わずかな自由時間も見いだせないほどに、みな追い立てられるような毎日を過ごしているということなのか。
そういう自分だって、生活から「寸暇」が消えて久しい気もする。余裕のない気持でいるつもりはないのだけれど、でもやっぱり何とは無しの忙しさの渦に巻き込まれているんだろう。
そんな「寸暇」があり、なにか映画でも観ようと思い立って、ちょうど空いている時間で観られる映画を探し、見つかったのが『年少日記』だった。
結果から言えばこの選択は大正解で、こんな時には、「寸暇」が生まれた偶然と、その寸暇を生み出すように過ごした自分の時間の使い方を喜びたいとさえ思える。
苛烈な幼少時代を過ごし、教師になった主人公が、自らの出自への振り返りを通じて、現在の生徒たちや家族との関係を見つめなおす。「トラウマを抱えた人間の内省的な成長物語」そんな風にまとめてしまうと、十把一絡げ感の強い作品群の一つのようにも感じ取れてしまうが、この映画には、そんな一括りでの観方を許さない、心象描写への細やかな配慮が行き届いている。
一見して感じたのは、「コミュニケーションの手段」を適切に描き分けることに、この映画が重心を置いている、という点だ。
つまり、人と人とが接する際の手段を、目的や局面に応じて適切に使い分ける、そうした配慮が劇中に丁寧に反映されていると思う。
具体的に言えば、発話をはじめとする「音声」と、筆記による「文章」、その2つのコミュニケーション手段の違い、それらの速度と熱量の違いが、場面に応じて適切に意識され、使い分けられているのだ。
まず「音声」については、リアルタイムでの伝達、急を要する、熱を帯びたじれったい気持を表現する道具としての側面が、非常に強調されている。
たとえば、自ら命を絶った名も無い人間をSNSで非難する、心無い多くの書き込みを目にした主人公が、いてもたってもいられず、自殺者の擁護を試みるシーン。ここで主人公は始めのうち、スマートフォンで文字入力を始めるのだが、途中で思い直し、音声入力に切り替えて、自分の声が直接届くことを期待するかのように熱をこめ、反論のことばを入力し始める。
また、何かの悩みを抱える生徒会長に対して主人公が、自らが実践するストレス解消法、街上の高台から大声をあげることを教えるシーン。ここでも、大人も子供も等しく大声を上げるという情景描写が観客へ与える視覚的インパクトをも理解したうえで、声の持つパワーを最大限に活かしている。
さらにまた、主人公の妻の職業が「声優」であることも、たぶんに暗示的だ。もともと、ぬいぐるみに話しかけるような「閉じた会話」の中に居た彼女は、主人公と出会い、対話を覚えながら、最終的には多くの人に自らの「開かれた声」を届ける職業に就いた。その一方で主人公は、学生時代、幼い頃の記憶に苛まれ苦しめられた心持ちを、教師に告白して助けを求めることができなかった、『「声」を適切に出すことができなかった』、と回顧する。この二人にやがてすれ違いが起こることを、説明的ではなく、しかし非常な論理性を保ち、彼らの声の出し方によって対比し暗示する、巧みな演出だと思う。
(実は、単なる「声」だけではなく「音声」と書いたのは、このお話の中では「音」もまた重要な役割を果たしているからなのですが・・・長くなってしまうので、こちらは割愛します)
一方で「文章」は、タイトルにもなっている「日記」がその筆頭にくるだろう。幼少の頃の苛烈な体験と、心に沈殿した思いの丈を、他人に届くか届かないか曖昧なままに書き綴り、やがて誰かの目に触れることに期待する。そんな、か細く弱いかもしれないが、しかしじんわりゆっくりと伝わっていく熱伝導のような、文章が持つ気持の伝播力が、ここでは最大限に活かされている。
また、物語の進行に大きく関与するキーアイテムとして登場するのは、校内で発見される、誰が書いたかわからない「遺書」だ。この「遺書」は、行き場のないメッセージとして、教師ならびに生徒の間に、じわじわと重い影を落としていく。そうしてその重きメッセージの推進力に手を引かれるように教師たちは、作者の探索を進めざるを得なくなるのだ。
いわゆるネタバレにならないよう、気をつけて書かないとならないのだが、この映画にはある「仕掛け」がある。
(映画を良く観ているファンに取っては、そう書くことだけで、大きなネタバレになってしまう可能性があるのは、意識をした上で)
そしてこの「仕掛け」が明らかになる時、観客は、それまでに無い喪失感に見舞われる。極めてエモーショナルでもありながら、しかしこのような仕掛けを施すことも含めて、ニック・チェク監督の演出は、多分に技巧的であると言える。
しかし、決してその技巧の腕前を誇示するのではなく、あくまで作中人物と、彼らを見つめる観客の心情に寄り添った技巧である点が好もしい。
これがデビュー作というニック・チェク、今後が楽しみな監督です。
最後にどうでも良いことを一つ。
日本で本作をリメイクするならば、主人公役は星野源で決まりではないでしょうか。
登場した瞬間の佇まい、憂いを湛えた寂しげな表情の似合うロー・ジャンイップが、登場時点からすでに星野源にしか見えなくなったのは、自分だけだろうか・・・?
鑑賞メモ


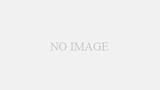
コメント