いまからおよそ20年前のこと、仕事やその他の事情で、頻繁に大阪へ足を運ぶことがあった。長期に泊まり込んで仕事をする場合、週末をまたいで彼の地で過ごすことも多かった。
そんな時、ふだんは味わうことの出来ない関西の映画館にいそいそと足を運び、歴史ある劇場や個性的なミニシアターで映画を楽しんでいた。いっぽうで、今日はちょっと芝居でも観ようか・・・と思い「関西ぴあ」を眺めると、選ぶというほどに演劇公演の選択肢は多く無く、また劇場についても、小劇団クラスが上演可能な小劇場がさほど見当たらないことに、違和感を覚えていた。
実際のところ、関西発の若手劇団は多くあったはずなので、どこかに上演する舞台はあったのだろうけれど、関東から来た人間が雑誌を手にしながら探す、というシチュエーションでは、かなりな苦労をするほどではあった。
演劇をはじめとする芸術活動に対する支援はどのように行われるべきか、これは非常に難しい問題だ。芸術に対して手厚い支援を行ってきた諸外国の真似をすればよいということでも無いのだが、劇場敷設と運営など、「場の創出」という面は特に、国や地方自治体による支援を期待したくなるところではある。
他方、才能ある者が経済的理由などで活動を断念しなければならない状況を少しでも軽減できるようにするための「人的な支援」については、さらに難しさが増す(だれを支援すべきなのか?芸術性の高低で判断する?とは言っても、それはどうやって測るのか?)。
社会全体の経済が冷え込んでいるような状況では、芸術のように「無くても良いもの」は優先度が下げられてしまうのも、また致し方ない面もある。
冒頭は過去の一時期の関西を例にとってしまったが、こうした状況はいまや地域に限らず国内に拡がっていると見え、関東圏であってももはや状況は同様ではないかと思う。
芝居を打つことがむずかしい状況が増えれば「食えない」演劇人が増え続けるのだろうけれど、これはなにも若手劇団に限った話ではなく、現状は、中堅の演劇人や劇団にまで及んでいるのだろうと思える。
たとえばブルー&スカイのように、数十年もの間、ナンセンスコメディに身を投じることを厭わずに進んで来たある種の「猛者」が、余裕ある作品発表の機会と環境とが得られていない状況というのは、喜劇好きとしては、目の前がどんどん暗くなるばかりだ。
ここ数年の間は、(演劇については)ほぼ年に1作ぐらいのペースで活動をされているが、しかし商業的に大ヒットするというわけでもない演劇人にして、年1作によって創作活動を継続する生活の糧を育めるのかといえば、はっきりいって無理なわけで・・・かと言って、興行のペースを上げれば良い、と、そう単純にはいかないところがなんとも・・・
もちろん演劇以外の仕事もあるのだろうけれど・・・芝居に関して年1作ペースを続けているのは、「昔の自作を読むと面白くて、新作を書くのが嫌になる」という本人の性格(それもまたブルー&スカイらしさではある)も、根底にあるのかもしれない。そうした作家としての創作課題が、興行のペースを決める理由の中でどのくらいの率を占めるのかどうかは、本人にしかわからないが、とにかもかくにも生活をしなければならず、そのためには安定した収入は不可欠であり・・・といった「生活優先度」の影響については、それが厳然と存在していることは間違いないだろう。
「食べなければならない」というレベルの解決策としてUber Eats配達員を兼任する(時にはそちらを本業と呼ぶべき勤務量で)ことを選ばざるを得ないという状況。
世が世なら、パトロンに抱えられる宮廷道化の如く、衣食住に満ちた余裕ある生活の中で、超絶くだらないことを練りまくっている日々もあったはずだろうに・・・と想像してしまうが、そんな想像は、ご本人にとっては超巨大なお世話だろうし、そんな優雅に創作を続ける生活だってそもそもお断りなのかもしれない。それでもやっぱり、彼の笑いを受け止め続ける観客の立場、それでいて、彼の活動を丸ごと抱えられるほどの財力も持たない一般観客の身からすれば、どうしてもそうしたことを2025年の演劇や喜劇の状況として、書き残しておきたくなってしまうのだ。
もう一つ気になる点は、劇場に足を運ぶ観客の高齢化だ。これもまたコメディに限ったことでは無いとは思うけれど、スズナリといえばかつては、比較的マイナーでエネルギッシュな若手劇団専用劇場といった様相で、詰めかける観客は圧倒的に若年層が多かったはずだ。しかし今回の作品で、劇場の席の多くを占めていたのは50代以上の層だと思う(自分もめでたくその層の仲間入りをしているわけなのだが)。
これには、チケットの金額やネットの普及による視聴対象の変化など、いろいろな要因があると思うが、20代30代の年代が足を運ばないことには、未来の観客が確保できないのは間違いないわけなので、ここにどんな手が打てるのかを考え続けなければならない(もちろん簡単ではない)。
だが・・・そんないろいろな憂鬱な気分を抱えて劇場に来る人間を、ただでは返さないのがブルー&スカイの実力行使力(?)だ。
ひとたび観始めれば、そんな暗い気持ちはどこへやら、普段の生活では99%口にしなくなってしまった言葉「くだらない!」が、自然にポロポロと口をついて出てくる。
なぜか?
あなた「股ぐら」という言葉を、2時間という短い時間の中で、濃密度で聞いたことがありますか?
そんな言葉を高濃度、強炭酸のごとく浴び続けた日には、身体に溜まった「くだらなさ」が暴発しないよう、「くだらねえ!」という叫び声を定時的に体外に放出しなければならず、これを怠れば、くだらなさで膨満し続ける我が身体の危険を容易に覚えることになるだろう。
あるようで無いようで、でもちゃんと存在するストーリーは、近作ではかなりな破綻具合で唐突に幕を引くことが多かったように思うが、本作に関しては、唐突感はあるものの、なんだかこれはこれで、ブルー&スカイ作にしては美しい着地の仕方だな、と思ってしまった。これは褒め言葉なのか、貶し言葉なのか、自分でも判断はつかないが。
鑑賞メモ


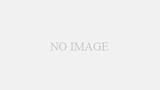
コメント